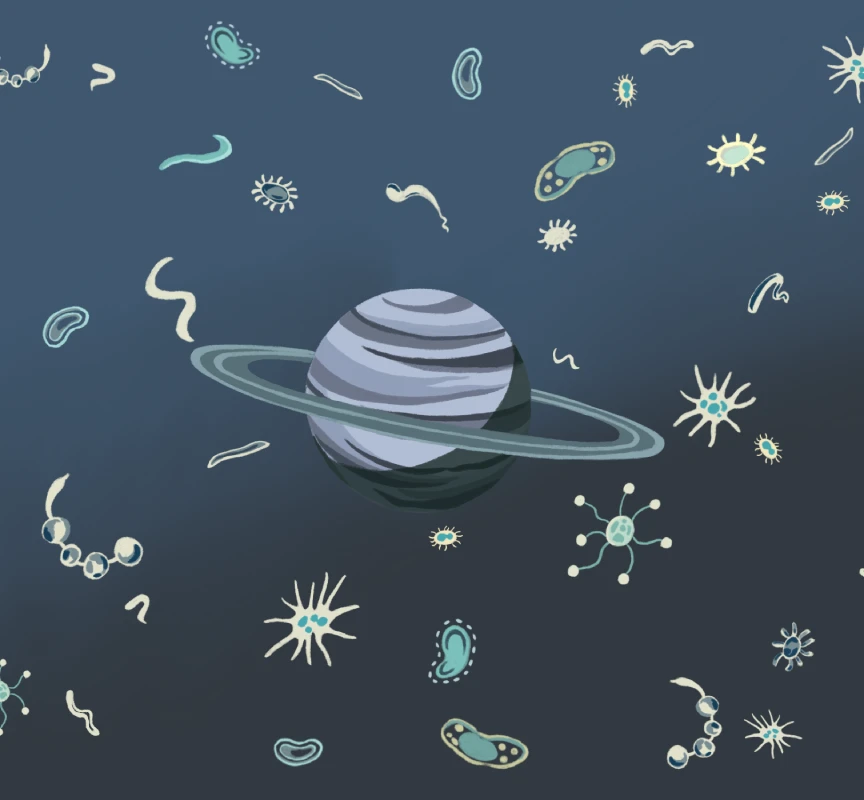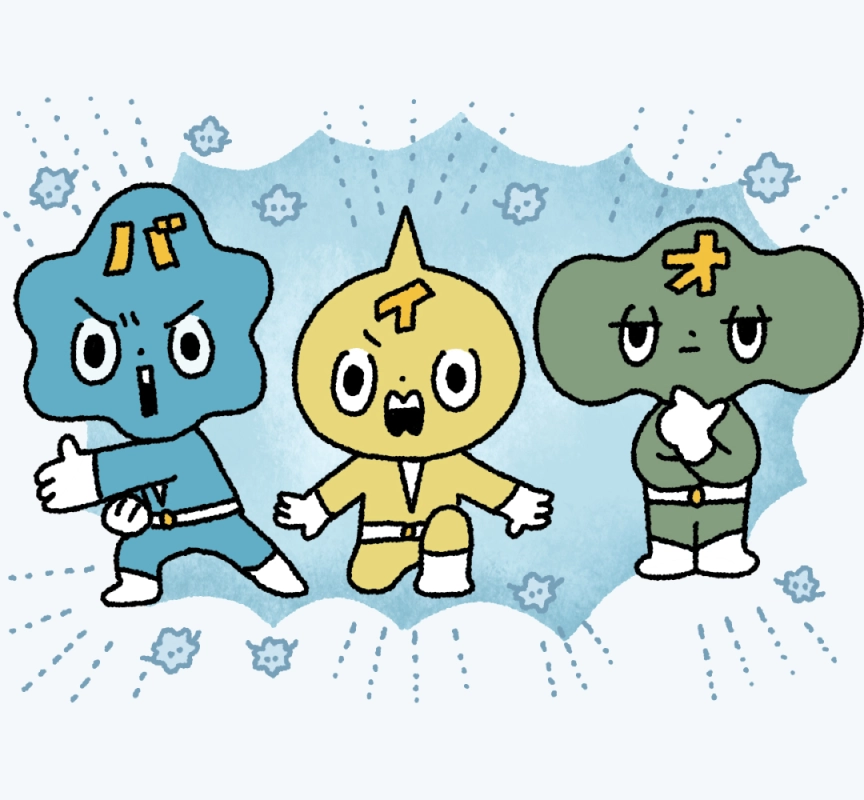Feature
微生物は「いま私と一緒にいる」。〈BIOTA〉伊藤光平さんに聞く、人と見えないものたちの共生関係

Index
第3号で触れた「発酵」。第4号では、その立役者である「微生物」の世界に注目します。電気、水道、ガス、電車、道路といった、私たちの暮らしを支える存在と同じように、実は「微生物」もインフラであると語る人がいます。
それは微生物の研究事業者であり、株式会社BIOTAの代表の伊藤光平さん。ランドスケープデザインや建築設計の際に、微生物の多様性を高める仕組みを取り入れることで、人々が健康で安心して暮らせる都市づくりを目指しています。
目には見えないけれど、私たちの手の上から、人やものが行き交う街にまで、確かに存在する微生物。彼らは、ときに脅威になることもあるけれど、私たち人間の生活にとって欠かせない存在なのです。
伊藤さんの視点から、すぐそこにある微生物たちの社会をのぞいてみましょう。
人間にとっての都市と、腸内細菌にとっての腸内は似ている
伊藤さんは研究の中で、都市の微生物を調査・解析していますね。私たちの住む街の、どこにどんな微生物が存在するのでしょうか。

伊藤さん
例えば、吊り革には人の手にいる微生物がいるし、トイレには人の腸内細菌がいます。都市の微生物は基本的に、その場所で人が何をしたかで決まるといえるのです。給湯や暖房のためにマンションや病院、オフィスビルなどで利用されているボイラーからは、砂漠にいるのと同じ種の微生物が検出されます。熱さに耐えられるようなものが生き残るんですね。同じように下水道には、流れてきたさまざまな化学薬品に適用できるような微生物がいます。人の行動は、実は見えないところでいろいろな生き物に影響を与えているんです。
挙げていただいたような場所には、具体的にどんな種類の微生物がいるのでしょうか。

伊藤さん
人の手には、例えば黄色ブドウ球菌やアクネ菌などがいますし、腸内細菌といえば大腸菌が代表的です。しかし、どんな種類の微生物がいるのか個別で理解するよりも、ネットワークとして見ることが重要です。例えば、腸内には500〜1000種もの微生物がいる。それらの相互作用に目を向けるのです。
人間だって、ひとりでいるときと集団でいるときで行動や意思決定が変わりますよね。ひとりひとりができることは限られているけれど、人々が集まり、互いに作用し合うことでいろいろなことができるようになる。そう考えていくと、人間にとっての都市と、腸内細菌にとっての腸内は、同じ「生活を営む空間」であると捉えることができます。スケールが違うだけで同じ構造だと思うのです。
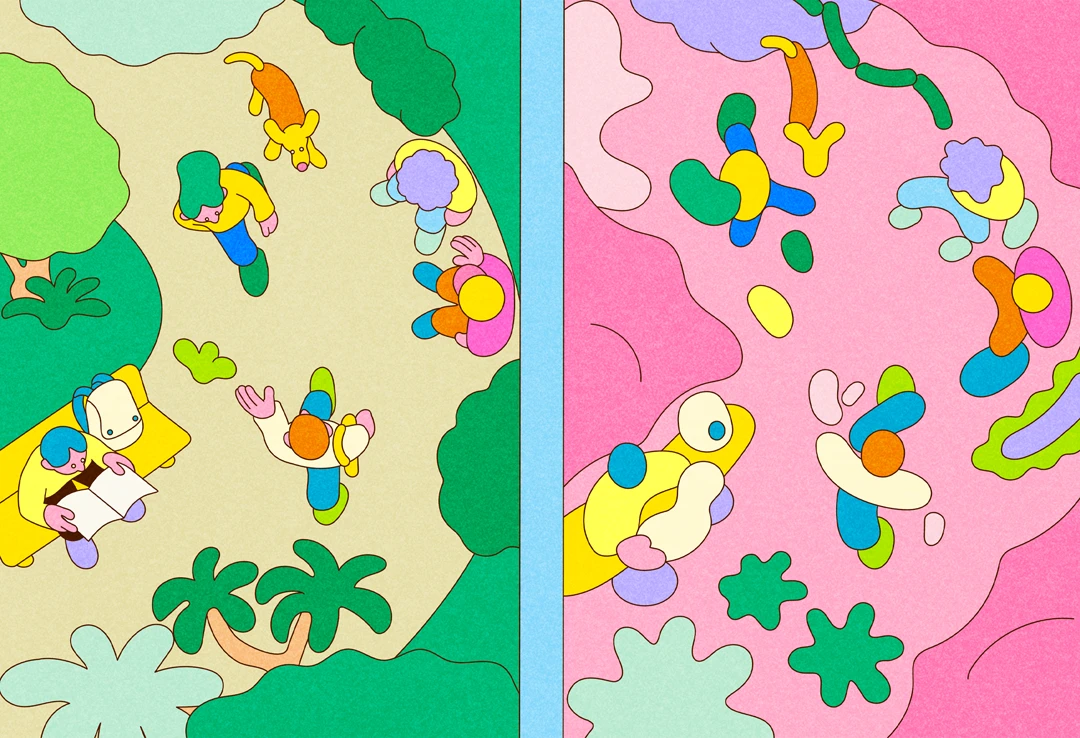
微生物の世界でも、私たちの社会と同じようなことが起きているんですね。むしろ、人間よりも遥か昔から存在している微生物の世界に、私たちの社会が相似していると考えるべきかもしれません。

伊藤さん
微生物の世界には、僕たちのそれよりも圧倒的に多様な社会があります。新しい種もどんどん増えてきていて、それはおそらく僕たちの研究よりも早いペースです。だから、「正体がわからないから除菌・殺菌しよう」という発想は限界に近い。
「わからないこと」を前提とした上で、それとどう向き合い、どう一緒にいられるか。そういう寛容さを持ち続けたいですね。そもそも、人の身体には約100兆個の微生物がいる。「いま一緒にいる」のです。
自然に対する「触れ方のセンス」を磨く
コロナ禍以降、これまでよりもさらに除菌や殺菌が意識されるようになりました。しかし排除するのではなく、人と微生物が共存する環境を考える必要があるということですね。

伊藤さん
過剰で不適切な除菌や殺菌を続けると、薬剤耐性菌を増やしてしまうことにつながります。つまり、病気に対しての抗生剤や、塗料、歯磨き粉、洗剤などに含まれる抗菌化学物質に、微生物が突然変異によって耐性を持ってしまうんです。そのような抗生物質で死滅しない微生物が生み出されてしまった環境では、むしろ感染症などの病気にかかるリスクは高まってしまいます。
僕は、都市における一番の微生物の発生源は人だと思っているんです。人は1時間あたり100万個ほどの微生物を放出しているといわれています。つまり、人が密集している場所は微生物の量がかなり多いということ。密室空間や公共空間で人から人へ感染症が移りやすいのはそういう理由です。
微生物の中でも、人由来のもの、自然由来のものは切り分けて考える必要があります。微生物にもそれぞれにすみかがあって、住める場所が違うのです。人に移る微生物は、人の体に棲んでいた微生物。それらは土の中には棲めません。
いま都市はどんどん過密になってきているので、人由来の微生物が過剰に増えすぎてしまっていると考えています。でもその総量を減らすことは、都市に人口が増えている以上難しい。だとすれば、人由来の微生物に対して競争的な環境を作る必要があるんです。つまり、土壌や植物などにいるような、自然由来の微生物を都市に増やしていく。そうやって微生物多様性を高める街づくりを実践していきたいと考えています。
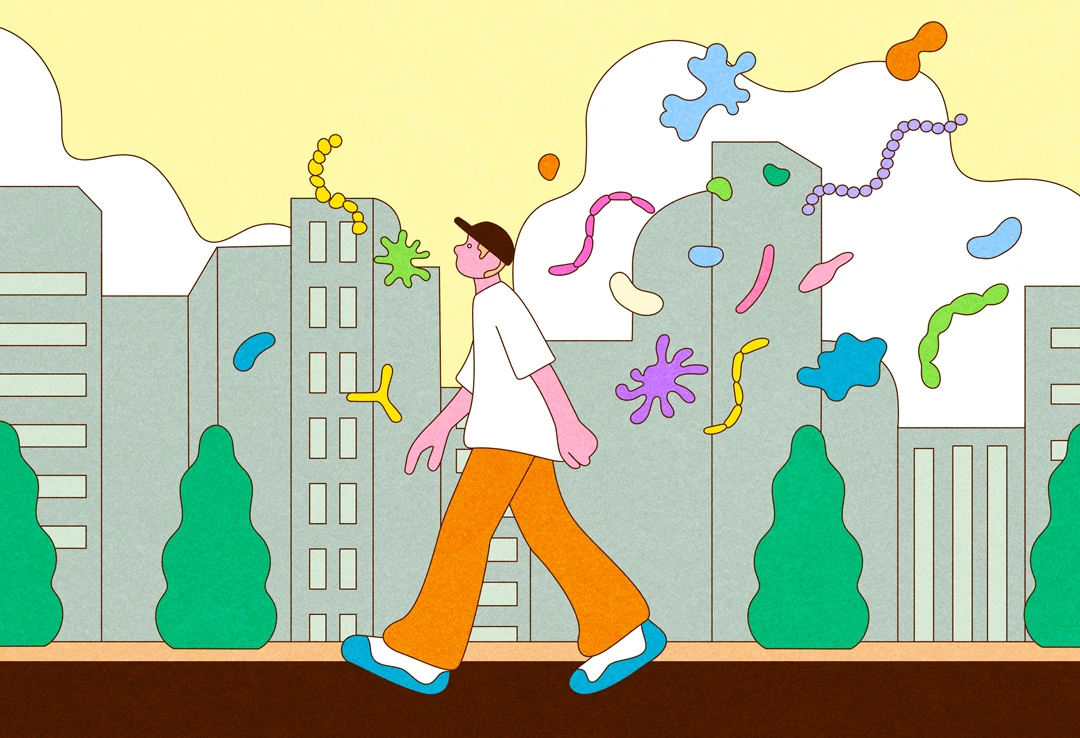
自然豊かな場所ではなく、あえて都市で微生物を研究することの面白さはどこにありますか。

伊藤さん
人間が建物を建てたり、街を作ったりすることは、その場所の生態系を壊してしまうネガティブな行為だというイメージがあるかもしれません。でも僕は、人間が自然に介入することは全く悪いことではなく、「触れ方のセンス」があればいいのではないかと思っています。もちろん、そこにいる生き物のことを考えずに強引に森を切り開く、というようなことには反対ですが、建物ができることによってむしろ生き物が住める場所が増える可能性は大いにあるんです。
人の介入によって、むしろ生態系が豊かになることもある。身近な例だと、ぬか漬けも人がかき回すことでおいしくなるといいますよね。

伊藤さん
漬ける人の手によってついている微生物が違うので味が変わるみたいですね。一方で、そのとき人も、ぬか床から微生物を受け取っている。微生物との相互作用は、僕たちが関心を持っているテーマの一つです。
一緒に住んでいる人と犬では、腸内細菌が似てくるという内容の論文のプレプリントも発表しています。同居しているカップルや家族もそう。腸内細菌が感情を決めているということもわかっていて、神経伝達物質のセロトニンやドーパミンなどの半分以上は、腸内細菌が作っているといいます。腸内細菌が似ることによって、感覚や感情が似てきてもおかしくはないんです。微生物を通じて、ある種の絆が生み出されているのではないでしょうか。
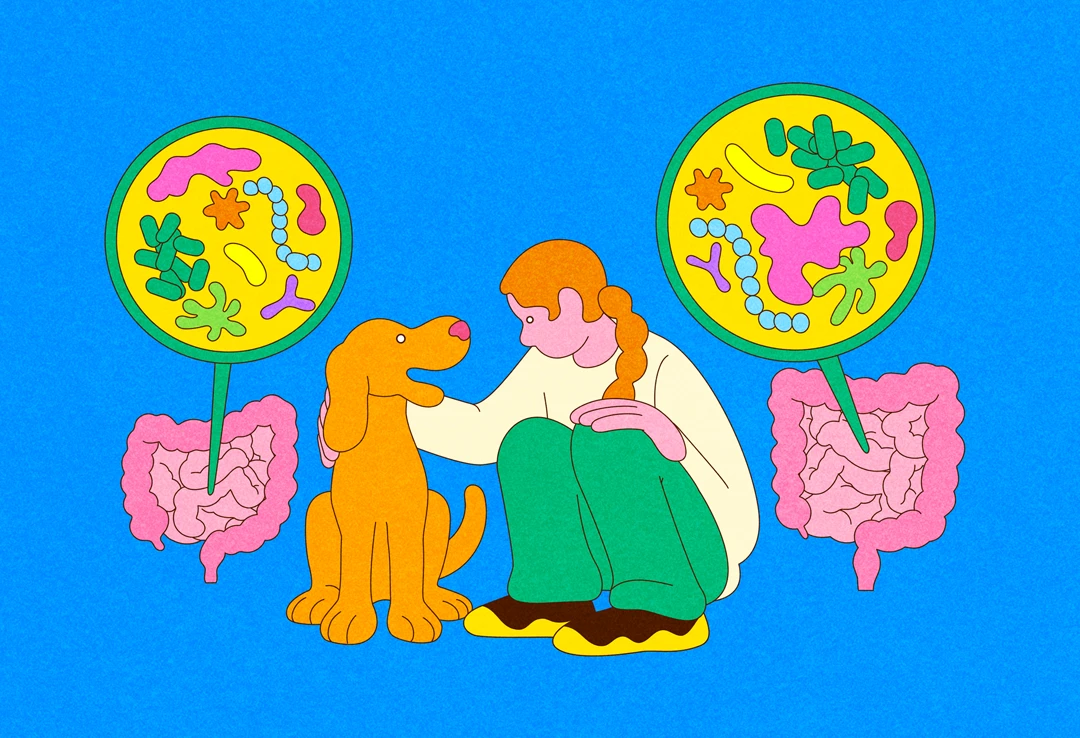
微生物は、都市のインフラである
微生物多様性を高めていくための取り組みとして、伊藤さんが開発された加菌器「GreenAir」が印象的でした。

伊藤さん
「GreenAir」で目指したのは、“都市にとってのヨーグルト”です。人がヨーグルトを通して菌を摂取し続けて健康になるように、都市に微生物を足していくようなものが作れないかと。でも「GreenAir」は、10〜20年という短いスパンで見たときに有効なもの。本当は「GreenAir」の必要ない世界を作りたいんです。意識的に加菌しなくても、都市の中に微生物多様性がある状態を作るのが目標なので、ランドスケープデザインや建築設計に力を入れています。
僕は、微生物は都市のインフラだと思っているんです。表に出てくるわけではないけれど、ないと困ってしまう、縁の下の力持ち的存在です。
日本科学未来館で開催された「セカイは微生物に満ちている」展への協力なども、私たちを陰で支えてくれている微生物の存在に気づいてもらうための活動なのでしょうか。

伊藤さん
僕たちのアティチュード(姿勢)として、「理性で探究して解決する」サイエンスと、「感性で探究して問いかける」アートの両軸を持っていることを大切にしています。ソリューションを編み出すだけではなく、次の課題を問いかけることが必要だと思っていて。研究者だけではなく、アーティストや料理人ともコラボレーションしているのはそのためです。

循環とは、多様な生き物や資源と共に遊び尽くすこと
私たちが生活の中で微生物の存在に気づくには、どのような視点が必要なのでしょうか。

伊藤さん
いま僕たち人間が微生物の存在を認識できるのは、顕微鏡やゲノム解析などの技術の進歩によるものです。でも、それは「人が実感を持って微生物が見えるようになった」ということではないと思うのです。
今後どれだけ人類が発展していったとしても、微生物が肉眼で見えるようにはならないですよね。だからこそ、「姿が見えない状態」で、微生物たちの営みにどう気づけるかということが大切なのではないでしょうか。
例えば、温泉のお湯が流れている場所が黄色や緑色になっている場合、そこは微生物が硫黄を酸化や還元させたのだとわかります。コンポストを使うと生ごみがいつの間にか消えているのも、日本酒づくりのときにお酒のもとになる「酒母」にポコポコと泡が立つのも同様です。微生物自体は見えなくても、実は私たちは、微生物とある種の対話をしている。そういうことに気づくチャンスは、日常生活の中にもあふれているんです。

「見えなくても、感じ取る」という感性を持ちたいですね。最後に、微生物とのサステナブルな関係性を築くためのマインドについて聞かせてください。

伊藤さん
微生物だけでなく、地球にはさまざまな生き物がいます。せっかく地球に生きているならば、僕たち人間が、もっと他の生き物に関わっていくあり方を探りたいんです。
この『月刊日本館』の創刊号にも寄稿したのですが、真の循環を目指すならば、僕たちが「捨て方のセンス」を磨くことが大事だと思っています。何かを使わないように我慢をするというよりも、使ったものを他の生き物に還すためにどう捨てるか。そのマインドを持てば、いつか地球の寿命が終わるまでは人間も生態系のかけがえのない一員として楽しめると思うのです。
循環や持続可能性を考えることとは、「地球の多様な生き物や、豊かな資源と遊び尽くす」ということなのではないでしょうか。


伊藤光平(いとう・こうへい)
慶應義塾大学 環境情報学部卒業。高校時代から慶應義塾大学先端生命科学研究所にて、特別研究生としてヒト常在菌のゲノム解析に従事。学部生時代には住環境における微生物コミュニティも対象としたメタゲノム解析に従事。大学卒業後、株式会社BIOTAを創業し、微生物多様性を高める都市デザイン事業を行っている。
イラスト:髙橋あゆみ